    牢獄の聖者 --- ホセイニー師の教え |
|
| (前略) そういう私に決定的なきっかけがあたえられたのは、第二次世界大戦の始まろうとしていた昭和14年から後のことです。私は参謀本部第二課の特別諜報員に選ばれ、はじめは蒙古、つぎは中近東地区に派遣されました。中央アジアおよび新疆省にはいりこみ、この地の回教徒の独立運動に協力するという、非常に困難な使命でした。はじめ、私の任務はチベット潜入でしたので、蒙古のラマ寺で約8か月ほどの特別訓練を受けました。一人前ラマ僧として、疑われないだけの修行を積んだのですが。 これも奇妙な宗教体験というべきかもしれませんが、国のために働いている秘密任務という職務をもっている以上、私の意識の上ではスパイ体験としての意味が強かったようです。 蒙古のラマ寺の生活は全く気持ち悪く、たいていの文化人なら食欲も元気もなくしてしまうことでしょう。衣服や食器は決して洗うことがありません。そして大半の人々は、生まれたときから梅毒におかされているのです。が、その生活にもなれ、意味一つわからぬラマ教のお経もなんとか覚えました。後もそうでしたが、私はニセ者であるために本者以上に必死に学びかつ行じました。バレないためです。しかしこれが私にはよかったのです。この苦しく、不快な期間に、私はそれまでに教えの受けたことのある中村天風先生、若林半先生、藤井日達上人、鈴木大拙先生、ビルマ独立の父オッタマ僧正や、大本教の出口聖師のことを思い出しました。この方々の教えをしのぶことによって、耐えぬいたようなものでした。 いよいよチベット潜入ということになり、同士とともに、五原の砂漠を越え、やっとのことで蘭州までたどりつきました。まる50日間砂漠を騎馬行したのです。 ところが、そこで襲撃され、同士は行方不明になり、私は回教寺院に逃げ込んで助かりました。この縁が私にイスラムへの目を開いたのです。私は日本へもどって具申し、イスラム圏工作の密命をうけてインドに渡り、ここではじめてヨガアシュラムを訪れ、ヨギたちと接しました。そのときには、将来自分がヨガ修行者になろうとは思ってもみませんでした。私はこの時ガンジー聖師にお目にかかったのです。 私がインドへ渡ったのは、インドからイランへ渡り、イランの回教徒のなかに加わり、中央アジアを通って、新疆省に潜入する勉強のためでした。 当時のイランはトルコにならって、宗教への弾圧対策をとり、外国人が宗教家たちと緊密に交渉するのを禁じているにもかかわらず、私は入国して早々回教徒長老たちに接近し、完全にマークされてしまったのです。とうとう便所にまで尾行がつくほどになり、私はいったんイラクに逃げてから、ふたたびイランに潜入しました。そしてそこで密告されて逮捕されてしまったのです。 私はペルシャの東北、ソヴィエト、中央アジアに近いメシエッドの郊外の牢獄のなかに投げ込まれました。足には2メートルほどの長さの重い鉄の鎖をつけられ、そのさきに半径30cmもある鉄のおもりがつけられています。歩くたびに「じゃり、じゃり」と音を立てる鎖が、自分の運命を象徴しているように思えました。 「死刑か、死刑でなくてもここから出られることはあるまい」 ここで私は、「秘密工作員になったら、殺されても行方不明で片づけられてしまう。どういう目にあってもいいという覚悟が身についてないなら、この道にはいるな」 という特別任務班の先輩たちの言葉をしみじみと味わいました。牢には20名ほどの入獄者がいたようですが、私は独房にいれられていました。 白髪の同房者 入牢して20日ほどたった日の午後、私の牢に、品のいいおじいさんがはいってきました。とても物静かで、牢にはいってくるときにも、まるで空に漂う白い雲のように、ふわっとはいってきました。まるで牢を楽しむという風情で、表情はゆったりとしていていつもほほえんでいるように見えます。そして、足には鎖がつけられていません。 どういう人なのだろう。よほどの地位にある人なのだろうか。それにしてもなんと、落ち着いているのだろう。 しばらくたって、私はたまらなくなって、声をかけました。ペルシャ語で、 「おじいさんは、どうして鎖がつけられていないのですか」 と聞くと、流暢な英語で答えてきました。 「刑がきまったし、私が宗教職のものだからだよ」 「禁固刑ですか」 今度は英語をつかった。 「いや死刑だ。君は密輸かね。ときどき中国人が密輸かコミュニストの疑いでつかまるそうだが・・・・・・」 「いえ、私は日本人です。密輸ではありません」 「ほう、日本人が、めずらしいな」 「おじいさんはどうして死刑になるのですか。殺人でもしたのですか」 「ははは、ちがうよ。皇帝の宗教弾圧政策に反対したので、反乱罪にされたのだよ」 おじいさんはまるで褒美でももらったようにうれしそうに見えます。人の世とは別世界の空気を持った人という感じです。へんな人もいるもんだなと私は思いました。 「英語がお上手ですね。どこで習われましたか」と尋ねると、インドと英国とフランスとドイツに15年間留学したと答えました。 私が黙っていると何もいいません。そばにいてもまるでいないような静かさです。ときどき「ビスミラワーヒ・ラフモーネ・ラヒーム」とか「アワラーホ・アクバル」というマントラをくりかえすだけです。 「やはり死刑がこわいのかな。恐怖や不安をのぞくために、冥想やマントラの口誦をするのだろうか」そう思いながら老人の表情を観察しましたが、おじいさんのふんいきは暖かで、ゆったりとしていて、しかもおごそかで、そういうせんさくをすることが恥かしいほどのものでした。おびえたような目とか、挙動、苦悩するような目の色は1度も見せません。溜息もつかず、あくびもせず、うなだれもせず、まるで菩提樹の下のシャカのように静かにゆったりと座っています。何日も相対していると、まるでこの人物のまわりに光の漂うような感じもしてきます。シャカやキリストの絵などにある、あの後光というのは、こういうものかもしれないと私はこのおじいさんに深い尊敬を感じるようになりました。 「おじいさん、あなたは死刑が確定しているというのに、平気でしかも朗らかに見えるのはなぜですか。死への不安というものはないのですか。あきらめると、おじいさんのようになれるのですか。」 5日ほどして私は尋ねました。 おじいさんは、私の覚悟がくずれてきたのを見ぬいているようでした。死刑の確定しているというこの人物が入牢してから、私は死の宣告が身近に迫っているのを感じて、だんだん不安になっていたのです。 「では、どんな心を持てばいいのですか」 「ふだんのままの心さ」 「そのあたりまえの心は、動物的なあたりまえの心だ。人間的なあたりまえの心とはどんな環境や立場におかれても、朗らかにしていられることだ。そういう知恵をもった心なのだ」 私は言葉がなく、黙っていました。おじいさんの言葉はほんとうだと思われました。それまでに習った禅も、それに似たようなことはいっていたように思いました。しかし、こんな切迫したときに聞いたおじいさんの言葉は、かって似たことを聞いたり、本で読んだりしたときより、数段重く、ずっしりと私の心に感じられました。このおじいさん自身が死を間近に控えて、ゆったりとしている完全なモデルであったせいもあるでしょう。 「人間心と動物心のちがいを、もう一度話してくださいませんか」 「いやなときにいやな顔をし、おそろしいときに不安な状態になり、腹の立ったときに怒るのは、動物にもできることだ。動物的自然心とでもいうかな。こんな心の持主にはだれもがなれるものさ。地のままでいいのだから、練習の必要もない。 しかし、困ったときにも笑っていたり、いやなことにも平気でいたり、自分にひどい仕打ちをした人でも愛したりする心を持つには、修行をしなくてはならない。人間心とはそういう練習を通じて身につけるものなのだ」 この教えは、私が父から幼少時代くりかえし聞いた言葉でした。私の父は欲情コントロールの名人でした。 「練習で心もトレーニングできるのですか」 「宗教の修行というものはそういうものだ。練習を積むと心は平和に満たされているので、不都合なことも起こらないのだ。君がつかまったのも、君の心の状態がそのまま態度に現れていたからだろう」 「いやあ、おじいさんはどうしてつかまったのです」 「ははは、私は部下が君のようだったのでつかまってしまったのだ」 私は問うことをやめ、おじいさんのやっている通りの行のまねをしはじめました。しかし、おじいさんの冥想は長くて弱りました。私はときおり目をあけて、おじいさんを眺めてはまた仕方なく閉目するといった具合でした。 だが、まねでも、冥想やマントラをしつづけるとたしかに心は鎮まってきます。禅寺での座禅、ラマ寺でのマントラによる統一、ヨガ塾での冥想行など、その一応の修行体験とここでの冥想体験とを、わたしはいろいろ比べたりしました。 たしかにこのような平静心でいっさいの場合に対応できるようになったら、どんなに良いかと思います。それには冥想がいちばんいいのだろうか。思えば、それまでの私はどこへ行っても考えることばかり多く、徹底した冥想行をつづけてはいませんでした。 人間心を作るにはと、冥想行のまねをして2、3日後、私はおじいさんにまた尋ねました。 「おじいさん。人間心を作るいちばん手取り早い方法を教えてください」 「それは信仰心をもつことだ」 信仰? 何かを拝むなんて、この私にできるものかと思いました。 「何かを拝むのですか」 「拝むのではない。いっさいを笑いと喜びと感謝で受け取る知恵のことを信仰というのだ。どんなことも、どんなものもこばまない。いっさいを神の与えたもうたものとし、神の教えとしてそのまま受け取るのだ。なるようになって結構とまかせきる感謝心で生きる。その心をもつことができれば、いつでも平静な心を保つことができる。そういう信仰をもつには、宗教の導きを受けるとよい」 「どの宗派でもいいのですか。仏教でも、回教でも・・・・・・」 「いいよ。同じ結論を教えているのだから。あらゆる宗教の結論は、悟りを体得した愛の行者になることだ。ところで君は、何教かの教えに従っているかね。神とは何かと、神を求めたことはあるかね。悟りとか愛とは何かと考えたことはあるかね」 神とか宗教とか愛という言葉を聞いて、私の心は鋭く刺されたような気がしました。禅をしたり、子どものころキリスト教の日曜学校に通ったり、母に連れられて寺へいき念仏を唱えたり、諜報任務のためにラマ僧のまねをしたり、比較的に各種宗教教団と接触する機会の多い幼少期であったにもかかわらず、心からそれを求めたことがなかったからです。そういうところへ行きながらも神を求める心はおこらなかったのです。 父の葬式のときには、坊主や寺が存在すること自体が欺瞞であると思い、小刀を構えて坊さんが家へはいるのを拒否し、母を泣かせたりもしました。 結核になって、天理教のひのきしん、金光教への参加、四国の霊場まわりも体験していました。このときは病気を治したい一心のせいか、治療への効果はあったようでした。しかし、これらも宗教への傾向の強かった母の考えに従ったものでした。実にいろいろな宗教とタッチしたものの、神というものを心から求めていたのではありません。神与というのでしょうか、つぎつぎといろいろな宗教教団との縁をもちました。そうして宗教の習俗とか、それぞれの特異な行法とかは知っているものの、宗教の実体である神については、「それはわかりません」 というしかないような精神状態でした。 まねごとをしすぎたせいか、安心立命、明鏡止水の境地にあると見えるこの優れたおじいさんに 「神を求めたことはあるか」 と聞かれたとき、私の心にはひとりでに罪悪感がわいてきました。神について考えたことはあります。しかし、神というものは存在しないというのが、ほんとうではないだろうかと思っていたのです。 「おじいさん、私は神とは何かを考えたことはあります。いろいろな宗教教派と接した経験も若いわりにたくさんあります。しかし、神というものが何かそれがわかりません。神とはいったい何なのでしょうか」 私はこのおじいさんから、神というものを教えてもらいたいと思いました。それはこのおじいさんのふんいきのなかに、何か非常に貴重な光が溶け込んでいるような気がしたからです。虚偽とか見栄とか服装などの形式とか、そんなものはみじんもなく、この世にあるよいものをすべて吸収しているという感じでした。この人なら、十分教えてくれるような気がしました。 土牢はうす暗く、部屋の大きさは10畳くらいでした。小さいランプがともっており、それにほのかに照らされて静かに語る白髪白ひげの老人の姿は、神々しくさえ見えました。私の質問に老人はにっこり笑いました。 「神とは何か、説明しろというのかね。私にはできないよ。私も若いころは、神とは何かと求め、一生懸命に読書などもしてみたものだ。ずいぶん法を聞いて歩きまわりもした。それがこうじて、一生をこの世界で送ることになってしまったのだ。青年時代は実業家になることを志していたのだがね。 若いころは、神とは云々とよくしゃべったものだ。そのころはわかっているつもりだったのね。すごい迫力だと人もいったよ。私は真剣なつもりだった。だが、そのころの私は、神を求め、神について語りながらも、心のなかにはすこしも安らぎがなかった。生活にも平和はなかった。 しかも自分では神をほんとうに信じ、神を知っているつもりだったから、ずいぶんもがいたものだ。 こうして、私の知った自分の実体は、まことにみにくく、いたらない姿だった。それに気づいたことが、自然に何ごとにもわび、何ごとにも感謝し、いっさいの縁を無条件に肯定して受けとれる心をつくってくれ、全受全托の無抵抗生活にいれてくれた。 そうしたら、どうだろう。なんだか知らないが、神らしいものを感じはじめてきた。そして生活のことごとくに、許されて生きているのだ、守られ、与えられ、愛されて生きているのだという味わいが生じてきた。救済の真意や悟りの実体もわかりかけてきた。 『自分は、はじめから救われており、いまも救われており、未来も救われる以外はないのだ』 と気づいたときはうれしかったね。 何もいまさらほしくはなかったよ。 そしたら、いっさいの縁がほんとうにありがたくなり、そのままにまかせて生きる気にもなってきた。こうして心がやわらいでくると、毎日の生活が楽しくてしようがなくなってしまった。 君は神とは何か考えるからわからないのだ。考えるのではなくて感じとれるようになるのだな」 私はおじいさんの話に、なにかしら真実を感じ、胸をうたれました。そして、つづけて質問することができず、夜も更けていたので、おじいさんも私も毛布の寝袋にもぐりこみました。 イランも南は暑いが、北は寒い。メシエツも、ときには東京ぐらいの寒さになることもあります。自分の姿を知ることから、わびる心、感謝する心、肯定の心、受け取る心が生まれ、神を感じはじめたという。淡々とした話だったが、その話は私に大きな期待と、これまでに感じたことのない底深い興奮を与え、頭が冴えていつまでも眠れません。私は大きなあこがれのために自分の心が涙ぐんでいるのを感じ、またそれに近づくには、いったいいまこの環境でどうすればいいのかと考えると、やはり心が乱れました。神を感じるというが、その神とはいったい何か、何を感じるというのか、そう思いはじめると、私の頭は 「何を」 「どのようにして」 という疑問でいっぱいになってきます。 現実をそのまま喜ぶ心 「おじいさんの話をうかがって、私もぜひ神を感じてみたいのです。一刻も早くです。昨夜寝床のなかで、神を感じたいと3時間ばかりがんばりましたが、どうしても感じませんでした。」 おじいさんはにっこりと笑いました。 「ほう、動物から人間になりたくなったのかな。でかした。でかした。」 それからちょっと間をおいて、 「だが、感じるのは神ではなく、神のみ心だ。」 といいます。そういわれて、私はまたわからなくなり、考えこみました。 昼食後、おじいさんが例のように経典を読みはじめました。わたしも素直にそれについて読むことにしました。 私にとっては、経典のなかではバイブルがいちばんわかりやすく、コーランがその次です。仏典は現代語以外はまったくわかりにくいものです。 アラビア語は世界一難しいといわれているし、コーランは1300年前の言葉だから、少しの勉強ではすらすらと解釈できません。しかし、日本語訳でだいたい覚えているので意味はわかりました。コーランのすべてを通じて教えているのは、神の徳をたたえることであり、「神は絶対なり、神は絶対なり、神におのれのすべてをまかせて従え」と強調しています。 こんな心境にはちょっと縁遠い自分であると思っていたのに、このおじいさんに会ってからは、この心さえつかみたくなったのでした。2時間の談後、おじいさんに尋ねました。 「もう1度お尋ねしますが、神のみ心を感じるにはどうしたらよいですか」 「それは現実をそのままに見て、それを喜ぶことだよ」 「この現実が、そのまま神のみ心なのですか」 「さよう、宇宙そのものが神だから、その現れのすべてが神のみ心だ。君たち若い者には 『自然』 という言葉を使ったほうがわかりやすいかもしれないね。 ほんとうの神を知りたかったら、自己流の見解や、自分で作りあげた神をまず捨てきる必要がある」 こういってまた冥想にはいってしまいました。 なるほど『自分で作りあげた神か。』 私は困ったときの神だのみの多かった自分を思いだしました。たしかに、何か頼みごとのあるときには必死に願ったりしたことが多い。この地下牢に入れられたときも、なんとか生命が助かるようにと必死で拝んだではないか。しかし、よく考えてみると、そういう力のある「神なる者」の実在を確信して拝んだわけではなく、ただ必死の思いで願ったにすぎません。 その願い心は、どうすることもできない立場から、祈らずにはいられない気持ちになり、自然に心の奥から出てきてしまったものです。 これが自己流の神というのだろうか、たしかに、自分で作り上げた神にちがいない。こんな祈りをしていたら、自分の願いのかなったときには神があると肯定し、そのかなわぬときは神なんかあるものかと否定し、平素は神のことなどすっかり忘れてしまっているという状態をくりかえす。神を信じている者の心は強いと聞いているが、それはなぜだろう。神は力を与えるものなのだろうか。自分のうちにも神があると聞いたが、私のうちの何がいったい神なのだろう。 そうだ、おじいさんは神は考えてもわからないといっていた・・・・・・。こんな考えが、ぐるぐると頭のなかをめぐりつづけます。 死刑もまた楽し 夕食後おじいさんのほうから話しかけてくれました。 「ええ」 私は力なく答えました。 「神とは何かは、自分でつかまえる以外にないものだ。それは言葉で説明できないものだし、たとえ説明してもらったとしたもわかりうるものでははない。神学は学問的なものだが、信仰は学問ではないからね。本を読んだり、話を聞いたりしただけではだめだよ。正しい生活の実行によって、次第に体得していけるものだ。だから信仰の深さは人によってちがうのだ。しかも、それは他人にはわからないことだ」 「正しい生活の実行について教えてください」 「心身を清め、心の目を開くには、実行しなくてはならないことが多いが、君がいちばんはじめに実行しなくてはならないことは、次の2つだ。 第一はとにかく笑い、とにかく感謝すること。 第二は自己流の解釈を捨てることだ。 「何にでも笑い、感謝するのですか」 「そうだ、無理にでも笑い、感謝しなくては、喜べる心はもてないではないか。しかも喜びの世界に生きる人だけが、神の世界を味わわせてもらえるのだからね」 「おじいさんは死刑になることも喜べるのですか」 「喜べるね。死刑にならなくとも、死ぬときがくれば、だれでも死んでしまうではないか。裁判は変わることがあるから、死刑にならないかもしれないしね。だから、わからないことでさわいだり、無理な考え方をするのを、自己流の解釈というのだ。また、たとえほんとうに確定して死刑になるとしたら、さわいでみても仕方がないことではないか。 どうだ、どうせ死ぬのなら、最後まで朗らかに生きてみたくはないかね。」 「そりゃあ。そうなれたらいいなとは心から思いますよ。だが死刑という最悪の場合にも、平気どころか、喜んでいる心までなれるものでしょうか。死刑を笑えるようなら、どんなばあいにでも笑えるでしょうね。どうしたら、いったいそんな心までなれるのでしょうか。」 「どうしたらって・・・・・・。ただ無条件に、どんなことでも喜びなさいと教えたではないか。そうなるにはいっさいのものの価値が理解できるまで、毎日、自分の知性と感性をたかめる工夫をしつづけることが必要だ。いいか。考えてわかることは、おおいに考えるがいい。いくら考えてもわからないことは、まかせるのだ。この二つの心をもつことが悟りだよ。」 「愚かな質問ですが、何にまかせるのでしょうか」 「その何にが、神にだ。若者には宇宙の働きといったほうがわかりやすいかな。あるいはなりゆきといったほうがわかりやすいかな。 私たちは、二つの運命が一つになって自分の運命になっていることを知る必要がある。一つは自分がつくりだすもの。もう一つは他から与えられるものだ。自分で作りだす運命は変えることもできるが、他から与えられる運命のなかには、どうしても避けられないものもあるのだ。だから、避けられない運命とわかったら、素直に神のお与え、神の導きとして喜んで受け取るのだよ。キリストのように」 「まちがっているね。君の考えは」 おじいさんは、すぱっとこう切り返してきました。 「まかせる心というものは、もっとも積極的な心なのだ。それは人事を尽して、その後の天命に従う心だからだ。善を最後まで尽くす心だよ。どうだ。君でも自分の全力を尽くして何かすることができたら、どうなっても心残りはないという気持ちに自然になるのではないかね。このときの心は平静だ。毎日、この真剣勝負の心で生きられたら、宗教心が身についたということができるだろう。 君は、生きているのではない、生かされているのだ、と気づいた生活をしたことがあるかね。生かされているということは、与えられているということだ。守られているということだ。救われているということでもある。この心が身についたら、すべてのことに感謝できるようにもなるだろう。まず、生かされて生きているのだ、という心に徹底しなさい」 おじいさんの話を聞いているあいだに、私の心は明るくなり、落ち着いてきました。このことをおじいさんにいうと、その心境が徹底したのが宗教心で、その心境をイスラム教ではファーナ(消滅の意味)、仏教ではニルバーナ(やはり吹き消されたという意味)、キリスト教ではアーメン(平和)と形容していると説明してくれました。 こうして、ひと月過ぎ、ふた月過ぎたある夜、私は夢うつつに騒音と罵声と銃声のいり乱れるのを聞いていました。その私をおじいさんがゆり起こしました。 「私の同志が迎えにきたが、君もいっしょに逃げるかね」 「はい、たのみます」 迎えの同志は、約30人ほどの騎馬団だったが、わたしにも馬1頭を与えてくれ、どこへいくとも知らず、騎馬団とともに暗闇のなかを走りつづけました。まったく予期せぬことで、私は救われたのでしたが、この夜のことを思い出すといまでも他人の西部劇を見ているような気がします。 次の日の午後、彼らのかくれ家の山家につき、そこに一泊しました。その夜、おじいさんが、 「君の中央アジア潜入の目的を達するためには、中央アジアにコネクションをもっているイスラムの托鉢団に加わるのがいちばんよいと思う。私の同志のひとりでシャラリーヤ派の団長をしている男が、いまイスパハーンにいるから、そこに行きなさい」 といってくれました。そして翌日、私は同志ふたりに連れられてイスパハーンに向かったのです。 途中、この同志たちにおじいさんのことを説明してもらいました。名はアル・ホセイニー師で、イラン宗教界の黒幕的な存在であるといいます。終戦後のいつだったか、イランのモサデク首相の騒乱があったとき、イランの黒幕として、このアル・ホセイニー師の写真とその紹介が大きく新聞に報道されたことがあります。私はなつかしさのあまり、手紙を出してみたいと新聞社や大使館を通じて、住所を調べましたが、わかりませんでした。 私はおじいさんに 「おじいさん、私もとうとう精神界の仕事にはいりました。私の胸中には、あのふた月のあいだ、おじいさんから受けた教えの数々が生きています。だんだんとおじいさんのおっしゃったことが、ほんとうだと思いはじめましたよ」 と感激の言葉をのべたかったのです。 ホセイニー師の淡々たる教えほど年若い私の胸を打ったものはなかった。私にほんとうの意味の宗教への目を開いてくださったのは、ホセイニー師とガンジー師であったと思います。またその人柄のふんいきが、20歳の青年にとっては、何よりも強いあこがれとなり、どうしてもその面影を求めざるをえなかったのを感じます。人は若いころに心から尊敬した人のようになるのだと私は思います。そして、私にホセイニー師が与えられたのは、どんなに感激しても足りないことだと思います。 師への感激の意を表する意味で、もう少し、師の言葉を列記させてもらいます。 「内なる神の働きとは、いのちの働きのことだ。いのちとは何か、と考えてもわからないだろう。こうして生きている現実そのものがいのちのあらわれだ。そうしていのちの真の姿は自分を最高に高めたときにあらわれるのであって、これが仏教でいう見性成仏だ」 その後、ヨガによって、神とはいのちなり、いのちとは自然なりと教えられました。ヨガ修行で悟りを開かれたホセイニー師の教えを受けていたせいか、それはすぐ私の心のなかに飛びこんできました。 「宗教とは、説明や思索や理屈をこねることではない。真実のみを求め、真実のみを愛し、真実のみを行うことだ。真実とは何かと考えてもわからない。求めるのだ、行うのだ、そうしてつかまえるのだ」 「信仰心とは、生かす心である。水を生かすのだ。空気を生かすのだ。物を生かすのだ。人を生かすのだ。そして、自分を生かすことだ。正しい栄養を取ることが信仰心であり、深呼吸することが信仰心である。金を生かすことが信仰心である。時間を生かすこと、場所を生かすこと、自己の才能や他人の才能を生かすことが信仰心である。」 この言葉は、信仰心とはどうしてももたねばならないものだと私に感じさせました。身体を生かすには、悪いものを食べてはいけない。無理な身体の使い方をしてはいけない。心を生かすには、悪いことを考えてはいけない。無理に心を歪めてはいけない。この事実を如実に実際に痛感させてくれたのが、ヨガ行法でした。 「真実の心を身につけたかったら、神とは何かなどを考えずに、ただ無心に祈りなさい。ただ無心に冥想を行いなさい。何かを求めて祈ってはだめだ。自分の考えや願いのすべてを投げつくすために祈るのだ。座禅するのだ。無条件の心になる訓練をしなさい」 「自分の心が空になったとき、神の心が自分の心になるのだ。心を空にするとは、自分のために祈らずに、神のために祈るのだ。イエスやマホメットは、いつも 『わが心を行うためではない。神のみ心をわが上になさせ給え』 と祈っているではないか」 自分のためにと思う心が湧いてきたら、私はこの言葉を思い出す。そして、心のけがれがぬぐわれていくのを感じます。 「君がどうしたらよいか困ったときの、手近な解決法を教えてあげよう。それは 『神はこんなとき、どのように考え、どのようになさるであろうか』 と静かに祈るか、冥想するのだ。この内省内観が内なる神の働きをよび起こしてくれるのである」 この教えは、ほんとうにありがたかったと思います。多くの人に知らせてあげたい教えのひとつです。「自他が神さまならどうするだろうか」 この心で受取り対処すれば、どんなときにも最善のことができるのではないでしょうか。 「ほんとうの愛とは自分を捧げる心だ。求めたら愛ではなくなる。求める愛は憎しみに変わる。無償の愛は喜びだが、有償の愛は苦しみの種になる。神の愛とは 『それでも愛する』 の愛だ。神の胸中は、好きも嫌いも、敵も見方もない。ただただ愛の対象そのものがあるだけだ。これが三昧心で、そむいたからと憎んでは愛ではない。いじめたからと嫌っては、また苦しめたからと怒っては愛ではない。神の愛を考えるとき、人間のいう愛などは、にせものだよ。愛などという言葉を使うこと自体におこがましさを感ずるね」 この言葉には一言もありませんでした。 「心のいちばんの苦しみは、対立心のあるときだ。君は相手のあやまってくるのを待つかね。それを待っていたら、死ぬまで和合はないだろう。君のほうからあやまっていくほうが、和合への門が開けて行く。動物にあやまる心はない。感謝する心とあやまる心を持っていることが、人間心に近づいたことだ。相手の救われと、その祝福されることまでを祈れるようになったら、信仰心といってもよいだろう。無条件にただ愛せるところまでいったら神の心だろう。この心にのみ、真実の喜びが与えられ、まことの平和の光が輝くだろう。和合するためには自己本位を捨てよ。自分の立場だけに立てば、だれでも言い分を山ほど持っているだろう。やめるのだ、言い合いを。それよりもまず、祈り合いなさい。無理にでもお互いが感謝しあうようつとめなさい。いっさいを神わざ、神の導き、神の教えと受け取ってね」 こうした言葉は、これまで私ひとりのためのバイブルでした。それをこのように多くの人々に知っていただけることを、私はうれしく思います。おそらくヨガについて私の書いたことのなかに、ホセイニー師やガンジー師の言葉とよく似た言葉を見つけていただけるでしょう。ホセイニー師やガンジー師の教えを、実際に体得していったのが、ヨガ修行でした。ですから、ホセイニー師のいわれたことと、ちがっているはずはないのです。師は回教で、私はヨガでも、なんの矛盾もありません。 ホセイニー師とガンジー師の教えは、私の信仰心への原点ともいえます。私は何かわからないことがあるたびに、この死を待つ土牢内での生活と、その中で会った師との会話を思い出します。 私はこのホセイニー師からイスラム教のことはもちろん、ゾロアスタ教ユダヤ教の関係についてもいろいろと教えていただきました。ヌベーダについていちばんはじめに私に教えてくださったのもこのホセイニー師でありました。ヨガでどのような修行をされたのかも話してくださいました。師はガンジー師の友人でもあったのです。私は、まだまだ数多くの教えを受けました。30数年前の教えのほとんどを覚えています。すべては私の心の中に、スーッとはいってきたものです。それは私が聞法するこころになっていたからであると思います。同じ教えでも、その教えのはいり方、理解の仕方、活用の仕方は、身構え心構えのちがいによってちがってくるのであると思います。 まず第一に生死の境にたたされていた私は、救われたい心でいっぱいだったのです。すなわち、求める心であったのです。(後略) 『冥想ヨガ入門』 沖正弘著 日貿出版社 1975年 より抜粋 |
|
トップページに戻る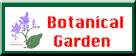 |