| 3.METAL GEAR SOLID (THE TWIN SNAKES) 1998年に発売された、METAL GEAR SOLID(PS版)。 この作品は、"CESA大賞 第3回 優秀賞"、"PlayStation Award GOLD PRIZE"、"ザ・プレイステーション・オブ・ザ・イヤー 第4位"、"文化庁メディア芸術祭 第2回 デジタルアートインタラクティブ 優秀賞 "を受賞し、1998年の日本語版発売後、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語と次々に各国語版がリリースされ、全世界で600万本を超えるセールスを達成した。また、映像、音楽、ムービー、ゲーム性などを新たに2004年にはNINTENDO GAMECUBEで"METAL GEAR SOLID THE TWIN SNAKES"として販売された。 Gene―"遺伝子" あらゆる生物のここの遺伝形質を発現する元になる領域で、遺伝により子孫へ細胞から細胞へ伝えられる。 この作品では、あらゆる戦い登場する―"蛇と蛇"、"人と機械"、"人と人"、"人と自然" そして、"遺伝子と遺伝子"。 事の発端もBIG BOSSという遺伝子、事の終結も遺伝子に関する復讐。 あらゆる意味で遺伝子という言葉はキーワードであり、この作品のテーマとなる言葉である。 どちらかといえば、MGSシリーズは"アクション"というジャンルよりも"RPG"のジャンルに近いかもしれない。綿密に構成されたストーリーと人間関係、実在する武器や機関などの登場と細かな設定が私のゲームの概念を打ち破るものだった。 だからこそ、私はこの作品について"ゲーム"ではなく、"映画"であると言うときがある。 ただ、映画はどうしても画面の向こうにいる役者が与えられた「役」を演じる"3人称"的要素が強い。 しかし、ゲームというのは、"1人称"的、"2人称"的である。 自分がコントローラーを握り、自分でプレイヤーを動かす。 対戦ゲームでは友達とも同じ空間を共有できる。 また、完成した"映画"というのは1通りのストーリーしか存在しないが、完成した"ゲーム"というのはプレイする人間の操り方でいろいろ変わる。 さらに、このゲームは大きなストーリーの中で自分が主人公になりきり、まさに現場にいるかのような臨場感を味わえる。 これは映画における役者の「役」を演じることと同じであろう。 つまり、このゲームは"Play (遊ぶ)"するのではなくて、"Play(演じる)"するゲームであると、私は思う。 このゲームがRPGに近いというのは、"Role Playing Game(役を演じるゲーム)"だからである。 つまり、MGSシリーズは役者が「役」を演じる映画とプレイヤーが主人公を動かすゲームが混ざったゲームであるといえる。 ただ、映画と大きく違うことが2つある。 一つ目は、このゲームでは監督=役者=観客であることかもしれない。 主人公の動きを判断する"監督"と主人公になりきって動く"役者"とその動きを即座に評価する"観客"、この3つがすべて自分であるということである。 二つ目は、演じる側に対して決められた台本というのがない。 (あるのは当然おかしいことで)そこに無数の方法でストーリが展開する。 敵の倒し方に関しても、"殴って気絶させる"・"銃で殺す"・"首を絞める"・"閃光弾で気絶させる"・・・・・・といろいろな方法があるし、別に敵を倒さなくてもストーリーは進む。 そこに、このゲーム特有の自由性が存在し、当時(1998年)その自由性を最大限に取り入れたゲームこそ"METAL GEAR SOLID"なのだ。 |
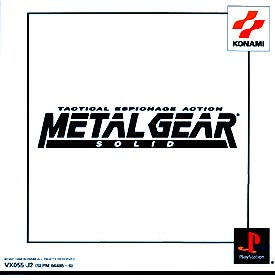 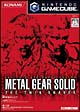 |
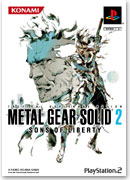 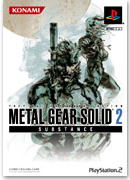 |
4.METAL GEAR SOLID 2 (SUBSTANCE) MGSが発売されて3年後の2001年にMGS2が発売され、"GAME AWARDS YEAR 2001-2002 優秀賞"を受賞した。 また、日本以外でもMGS2の評価は高く、アメリカのPS2専門誌「PSM」2月号にて2001年に発売されたゲームを対象にベスト10を選ぶ「PSM10」アワードの頂点に輝き、欧州での目標の100万本を大きく上回る初回受注157万本を達成した。 さらに、MGS2の発売からの1年後に"METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE"が発売された。 Meme―"利己的遺伝子" "Gene"が生物学的な遺伝子ならば、"Meme"は社会学的な遺伝子といえる。 利己的遺伝子は、生物学者リチャード・ドーキンスが提唱した考え方で、遺伝子は自分が生き延びるためにプログラムであり、あらゆる生物は自らのコピーを残すために作り出した「乗り物」に過ぎない。 自分のコピーをより多く残すために乗り物を作り、その乗り物がほかの乗り物や環境の中でうまく生き延びられるように操作するというのである。 このテーマはとても難しく、"遺伝子"の概念の違いによってこの考え方を受け入れがたいところがあるかもしれない。 ただ、簡単に具体的な例を挙げて説明すると、生物学的には親の遺伝子の一部を子は受け継ぐが、親の性格や意志などまでは受け継がれない。 だからこそ、人間には親への反抗期が存在して、親の思い通りにはいかないのかもしれない。 ゲーム性についてあげるならば、3年の間にMGSは大きく進化したといえる。 細かな行動設定は前作のMGSのリアリティを上回り、行動パターンを増やし、MGSの攻略パターンが∞ならMGS2はその∞倍といえる。 映像や音楽も映画並に迫力があり、キャラクターの表情からもそのリアリティの高さを窺い知ることができる。 たが、MGSよりもバックグラウンドは複雑になり、何度プレイしてもわからない部分が多かった―「愛国者」・「S3計画」・「恐るべき子供たち計画」・・・・・・etc。 ただ単にゲーム性を楽しむなら必要ないかもしれないことだが、一人のメタルギアファンならそのストーリーを完璧に知っておきたいし、小島監督の訴えようとしていることはこれから生きていくうえで非常に参考になる考え方である。 続いて、MGSが取り上げる諸問題について考えてみる。 |
| 前へ ■ 次へ |