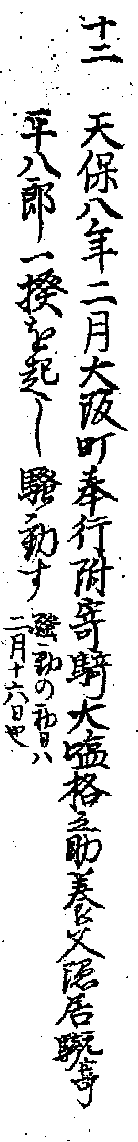Я[大塩の乱 資料館]Я
2001.3.7
玄関へ
大塩の乱関係史料集目次
『 桜 斎 随 筆 』 (抄)
鹿島則孝編著
鹿島則良・深沢秋男監修
本の友社 2000 「第1巻」所収
◇禁転載◇
| 桜 斎 随 筆 巻二 上 (抄) | |
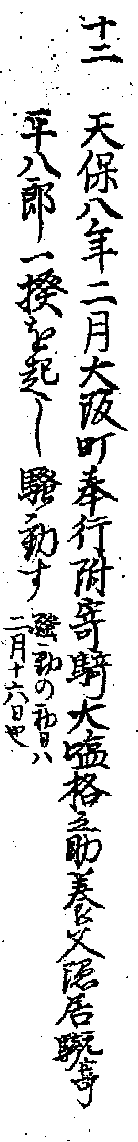
鹿島神宮
桜山文庫蔵 |
(釈 文)
一二 天保八年二月大阪町奉行附寄騎大塩格之助養父隠居 元寄騎平八郎一揆を起し騒動す 騒動の初日は二月十六日也 *1
目 録 (抄)
第1冊 桜斎随筆
桜斎随筆 巻壱
目録
月雪花之部 上
第2冊 桜斎随筆
桜斎随筆 巻壱
目録
月雪花之部 下
第3冊 桜斎随筆
桜斎随筆 巻二上
目 録
壱 則孝略履歴 附 さち子改名 則文元服 父子三人参宮
弐 則峯君鼠を愛せらる
附 下僕の幻術 則瓊君御性質 同御筆記 則孝武術流名
参 白蘭和尚
四 幕府の流鏑馬
五 野鷹屋に入る
六 鹿島大雪
七 江戸城中妖怪
八 江戸市中大火
九 大猿の造り物
十 江戸城焼亡
十一 筑紫家霊社号
十二 大塩騒動
十三 白気出現
十四 江戸市中大火
十五 日輪二出る 附 関東洪水
十六 妖星出現
附 強風 地震 信州大地震 諸国風災
十七 安政元年大地震
附 豆州紀州洪波 同二月大地震 同三年暴風雨
十八 水戸浪士井伊直弼を殺害 附 浪士鹿島神宮狼藉
(後略)
| |
| |
『桜斎随筆』は、全54巻60冊、 第66代鹿島神宮大宮司・鹿島則孝(桜斎 1813−92 かしまのりたか)が遺した幕末〜維新期の記録です。「はしがき」には明治20年4月が記されていますが、それ以前から折々に書き留めていたものです。昨年より復刻版の刊行が開始されました。近世日本の歴史・風俗・文化研究の史料としても興味深いものです。
花を愛した則孝は、明治18年4月、月瀬の梅、大阪の桜など花見の旅に出て、天王寺・生国魂杜・天満天神・桜宮をめぐっています。(このあと7月、淀川の大洪水で「なにわ三大橋」は破壊され、則孝の見たであろう周辺の風景は失われました。)
旗本・筑紫家に生まれた鹿島則孝は、天保8年に鹿島神宮第65代大宮司・鹿島則瓊の養子となっています。同年に起きた「大塩の乱」は、記憶に残るものだったようです。
また、則孝を継いで第67代鹿島神宮大宮司になった鹿島則文は、大塩平八郎と交流のあった近藤重蔵の子・富蔵と八丈島で流人生活を共にした人で、富蔵の『八丈実記』に序文を寄せています。伊勢神宮大宮司の職にあるときは、大塩が著作を奉納し、講義を行なったとされる「林崎文庫」にも関わりました。
『桜斎随筆』と「鹿島則孝」についての詳細は、「日本文学研究所」内、深沢秋男氏のサイト「鹿島則文と桜山文庫」(http://koudan.com/kashima/index.html)でご覧いただけます。
Copyright by Akio Fukazawa 深沢秋男 reserved
管理人註
*1 「大塩の乱」は、天保8年2月19日決起。
大塩の乱関係史料集目次
玄関へ