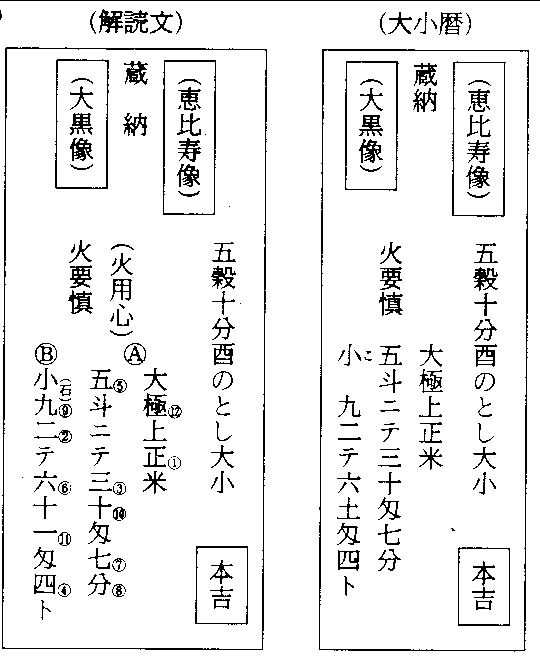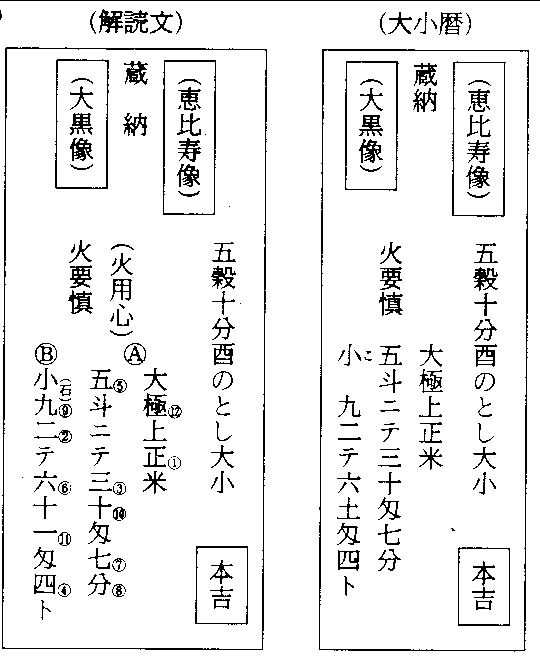Я[大塩の乱 資料館]Я
1999.7.20
玄関へ
大塩の乱関係論文集目次
「大塩事件一五○周年展」雑感
島野 三千穂
『大塩研究 第23号』1987.12より転載
◇禁転載◇
*表については一部変更を加えています。(管理人)
(1)「ときならぬ浪花の花火」に就いて
「ときならぬ浪花の花火」(以下、「花火」と略称)は一市井人の袋綴の写本に記された題名だそうです *1。 当時の一庶民の命名した「花火」が「大塩事件一五○周年展」(以下、「一五○周年展」と略称)で採用されて甦ったのです。ただこの「花火」は文学的表現であり、事件を美化したように解釈される面も少々有ります。しかし主催者の意図がそこにないのは次の説明で明らかです。京都の農村の十七歳の青年は檄文を「神鑑」(目録九九、以下、目録略)と名付け、類焼にあった大阪天満宮の神官は大塩を「神敵」と日記(一○四)に書付けた如く、大塩事件を「花火」といみじくも名付けた人があったのです。反乱と見るのでなく、又逆に共感するのでなく冷静にしかしかすかな好意を寄せつつも事件を季節はずれの花火にたとえるユニークさに、当時の庶民の感覚がある *2と紹介しています。因に花火とは線香花火でしょうか打上げ花火でしょうか。ときならぬと言うからには後者でしょう。(打上げ花火から連想すると)「花火」は全市街地の五分の一を焼いた「大塩焼」(一一三〜一一七)では有り得ない。棒火矢、炮碌玉、鉄砲などの「砲火」(一二三〜一三二)が「花火」の表現にぴったりであると思います。
(註)
*1 井上薫「時ならぬ浪花乃花火」一四七頁(『近世の摂河泉』創元社 昭和五十五年五月十日)
*2 「ときならぬ浪花の花火」出品目録及び紹介文(大阪城天守閣発行 昭和六十二年三月二十一日)
(2)内容分析
「一五○周年展」の開催の労をとって頂いた大阪城天守閣に先ず感謝の意を表します。さて「一五○周年展」分析にあたっては十年前開催の「第七十三回特別展 大塩平八郎 *3」(以下、「特別展」と略称)及び今年同時期開催の「大塩の乱と能勢騒動 *4」を比較対象にする必要があります。次表に見る如く、全般的には次の事が結論付けられます。
(A)「特別展」が書状、漢詩、学問、役職、肖像画など大塩を中心に据えて展示して居るのに対し、「一五○周年展」ではむしろ、門弟などの事件関係者や遺族等に関する新資料紹介に力点を置く様になって来て居る。
(B)「一五○周年展」では大砲など十点も出品され、視覚に訴えて効果的であった。火縄銃砲術実演会も含めて、沢田平氏、堺鉄砲研究会に負う所が大きい。
(C)「一五○周年展」では事件鎮圧側の支配文書(二一五−二一六)も僅かであるが出始めて居り、今後に期侍が持てる。
(D)「特別展」では市井の騒動伝聞書、風説書、触書、届書、吟味書、裁許書など、又はそれらを編纂した写本を厭わず展示して居るのに対し、「一五○年展」ではある程度ふるいにかけて、厳選して展示して居る。
(E)「特別展」では近現代関係著作の紹介が少い。
(F)「一五○周年展」では能勢騒動の展示が皆無なのが惜しまれる。逆に「能勢騒動展」は大塩事件も展示して居る。
(G)「一五○周年展」では数的分析にあらわれないが堀文書*5(七二−七四、七九−八五)が目新しい。この文書 は直接に事件とは何の関係もなく、当初、余り注目もして居なかった。しかし(当時の写本類が権力を恐れて殊んど無記名であるのに対し)筆者堀鉄蔵の出所も 明白で、当時の庶民がどのように事件をとらえていたかが分り、貴重であると感じる様になった。記述の正確さは仁風大平録*6(二三六)でも確められて居る。
| 資 料 展 名 | 会 期 | 会 場 |
|---|
| A | 第73回特別展 大塩平八郎 | S51.10.9〜51.11.15 | 大阪市立博物館 |
| B | 「ときならぬ浪花の花火」大塩事件一五〇周年資料展 | S62.3.21〜62.5.10 |
大阪城天守閣 |
| C | 大塩の乱と能勢騒動 | S61.12.21〜62.2.23 | 池田市立歴史民俗資料館 |
資 料 内 容
| 大塩事件 | 大塩事件 | 大塩事件 | 大塩事件 | 大塩事件 | 大塩事件 | 大塩事件 | 能勢騒動 | 合計 |
| 書・詩・学
問・役職・
大塩全般 | 世相・施行 | 事件 | 塾・門弟・
大塩の親類 | 事件の鎮圧 | 編纂物・伝
聞書・風説
書等々 | 近代・現代
の関係著作 | | | |
| A | 138
(40.1%) | 21
(6.1%) | 22
(6.4%) | 28
(8.1%) | 6
(1.7%) | 112
(32.6%) | 13
(3.8%) | 4
(1.2%) | 344 |
| B | 67
(23.1%) | 18
(6.2%) | 49
(16.9%) | 65
(22.4%) | 18
(6.2%) | 19
(6.6%) | 54
(18.6%) | | 290 |
| C | 7
(31.8%) | 1
(4.5%) | 5
(22.7%) | | | 1
(4.5%) | | 8
(36.5%) | 22 |
(註)
*3 「第73回特別展 大塩平八郎」(大阪市立博物館発行 昭和五十一年十月九日)
*4 「大塩の乱と能勢騒動」(池田市立歴史民俗資料館発行 昭和六十一年十二月十二日)
*5 中瀬寿一・村上義光「京都と大塩事件(上)(中)(下)(『大阪産業大学論集』社会科学編六五−六六、六八号 一九八七)
*6 註*5六五号参照
(3)大坂の与力同心研究の必要性
江戸の町奉行所の与力同心は風俗史の面に至るまで、実に良く研究されて居る。たとえばどんな服装をして居たか風俗画まで復元されて居る *7。捕具の十手の房紐の色まで与力同心で区別がわかって居る *8。大坂はどうか。町与力の服装さへ、平常時も出役時も不明であると言う *9。加えて、大塩に代表される町与力と坂本鉉之助に代表される城付与力の違いの考察もされて居ない。あらゆる面での大坂の与力同心研究の遅れは、大塩研究の片手落ちである。会期中「大塩の職業は何でしたか」と言う質問を何度も小耳にはさんだ。西暦一九九三年開催予定の「大塩平八郎生誕二○○年記念展」には是非とも、大坂の与力同心の十手を房紐付きで展示して欲しい。それを見れば時代劇好きの人なら、その職業はある程度、察しがつくだろう。
(註)
*7 笹間良彦「江戸の司法警察事典」(柏書房 一九八○年十月二十五日)
*8 名和弓雄「時代考証百科 捕者道具編」(新人物往来社 昭和六十年三月二十五日)
*9註*8 一四六頁 参照
(4)陽明学
会期中、懐徳堂のシンポジウムで研究発表された日本思想史研究の荻生氏が来城され、私的に懇切丁寧に大塩中斎の思想 *10について教示を受けた。難解であった。この方面の基礎的な論考も、これから大塩研究にどんどん掲
載して、「天満組風の我侭学文(問)?」を究明して欲しい。
(註)
*10 荻生茂博「大塩中斎の思想的位置」(『日本思想史研究』第十七号 東北大学文学部日本思想史学教室)
(5)道教
大塩平八郎画像の内、菊池容斎(一−二)(模写)のものが(定紋が大塩の丸に揚羽蝶だから*3)一番信憑性が高
いのではないか。いかにも精悍な面構えだ。傍に渾天儀が置いてある、天体の運行を観察する為の器機である。
「朝は常に八つ(午前二時)に起きて天象を観、門人を召して講論す*11」がそれを裏付けて居る。又、塾を洗心洞
と名付けている。洞といういうのは仙洞御所の洞と同じで、「仙人や道士の居る所*12」という意味がある。天体観察と言い洗心洞の命名と言い、この二つの事実は大塩と道教思想の関係を推測させるではないか。
(註)
*11 岡本良一「大塩平八郎」(創元社。昭和五十年九月十日)六三頁参照
*12 小学館「日本本国語大辞典」昭和五十六年九月二十日
(6)落書(ラクショ)研究の重要性
落書(ラクショ)とは匿名で権力を批判したり、社会の風潮を批判する事だ。従って、色々な文学形式があった訳だ。ただその伝達方式として、大小暦 *13の手法が良く用いられた。
(イ)大小暦(七二)
現代でも小の月はニ②シ④ム⑥ク⑨サムライ⑪と記憶して居る。江戸時代三百年間に現代と同じ大小月の配列の年はたった三回しか無かった。偶然にも、天保八年がそれに当ってニシムクサムライである。堀文書の奇麗な多色摺りの恵比寿・大黒像の一枚物がそれだ。それを解読すると左記の如くなる。
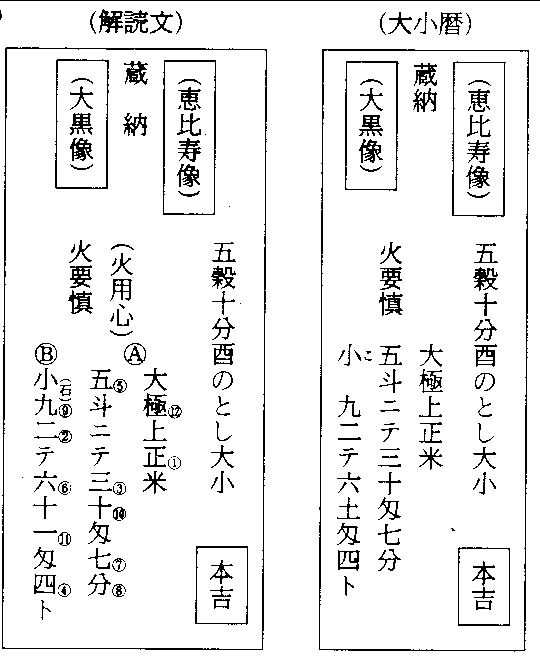
(A)大の月 五斗=三十匁七分
(B)小の月 一石=三十匁七分×二=六十一匁四分
(註)
(イ)極は極月で十二月。
(ロ)正は正月で一月。
(ハ)分は
八と刀で構成。
(ニ)トは分の崩し字。
(ホ)小九ニテ→石にて
(ロ)落書
「豊年歌天保八年酉五月ニ売ニ来ル写」(七九)は先ず天保八酉年を一首の狂歌に読み込んだあとで、各月ごとに大小暦を十二首に読み込んでいる。狂歌の一字か弐字目に漢字を使っているのは漢字が大の月を示して居る。
大小暦の狂歌だとすると「五月二売二来ル」と言うのは偽になる。新暦を使う現代でも五月にカレンダーは買わないだろう。権力を配慮した堀鉄蔵の自作の落書ではなかろうか。紙数がないので解読は割愛する。読者の方で研究されたい *5。
(註)
*13 新人物往来社「万有こよみ百科」昭和四十八年十月九日 四一三頁参照
(7)大塩の筆蹟
大塩の漢詩入門講座をして下さった先生には悪いが、大塩の漢詩(二三〜二五、二七〜二八、三二)はおいそれと読めるものではない。しかも、同一の人物なのに筆蹟が微妙に違って居る事が今回の展示で分りだした。何故か。年齢による筆蹟の変化か。偽物か。偽物だというのは格好が良いし簡単だ。一人が言いだすと右にならえの傾向さえ生じる。しかし案外、本物である場合もあるのだ。本物を偽物と言うのは罪深い。偽物を本物だと言う方が罪は軽いのだ。先ず確実と思われる筆蹟を大塩の著書等より抽出して、年齢別に、整理して、完全な筆蹟辞典を作成する必要があると思った。
(8)左殿文書
同文書 (一四六〜一八二)に大塩門弟の履三郎宛岡本大三郎書状(一五一)がある。岡本大三郎は東町組同心
で履三郎と親類であった。昭和五十九年に江川文書の中から大塩関係手紙の写しが発見された。その内の「口上覚」の中に「御組同心盗賊召捕掛り岡本大三郎」が盗賊共の面体に灸をすえた為、不調法を佗びた箇所がある *14。与力の大塩と同心の岡本大三郎と豪農で門弟の西村履三郎の間に何かの秘密があったのだろうか。猶、会期中西村履三郎の子孫である寺川氏(奈良県在住)が名乗り出られた。系図を拝見すると、左殿家より詳しい記述もあり、今後の研究にまちたい。
(9)墓碑銘研究の大切さ
会期中、T氏より大坂定番王造口、公用人、畑佐秋之助の墓碑銘の教示を受けた。又小生が偶然、大塩事件記載の平野郷町、末吉平左衛門の墓碑銘を見つけた。別の機会に御紹介する積りである。(住吉古文書教室)
(註)
*14 青木美智男「史料紹介 箱根山麓豆州塚原新田で発見された大塩平八郎関係書状類」(『日本福祉大学研究紀要』五九号 一九八四年)
Copyright by 島野三千穂 Michiho Shimano reserved
大塩の乱関係論文集目次
『大塩研究』第20号〜第25号目次
玄関へ