山
口
孫
三
郎
ほ
か
山口孫三郎 友松勘之丞 斎藤力蔵 其方共義、大坂町奉行組与力平山助次郎吟味中、孫三郎は預申渡受る 身分、勘之丞・力蔵は助次郎番渡し罷在上は、別して入念べき処、力 蔵は母りの病気にある迚、乍暫も勘之丞へ頼合せ宅へ立戻り、同人は 力蔵不居にも無頓著便用に相越し、両人共其場を明候故、助次郎儀番 人詰所棚に差置刀箱脇指取出し、自殺致す仕儀に至り候段、心付方 不行届一同不埒に付、三人共押込申付る。 多助 弥助 尭閣代兼慧寛 鈴木瀧太郎 庄司八十八 門蔵 其方共儀、不埒の筋も不相聞候間、一同無構。但多助・弥助は跡部山 城守家来へ渡し遣す。
平
山
助
次
郎
一、平山助次郎儀、組風の旧弊奉行存寄を以、改革可致は素の儀に 在処、組内勤向未熟又は我意申募る風儀に拘はる者は、組替申付可有 之旨の風説承り、身分の掛念は無之なれ共、自然右の通に成行くなら ば、向組へ対し不外聞の儀と歎か敷と存じ、且は向組の者共取計ふ向 をも疑惑いたす折柄、兼ねて学文心得方を教示受け、随順罷在る同組 与力大塩格之助養父大塩平八郎、右風聞の趣等彼是及噂を承り、弥々 心得違存迫り、殊に平八郎儀相聞弟子渡辺良左衛門等を以て異変の節、 心掛の儀度々相尋を難心得存じ、容易に組内の者へ応対難相成、役柄 も不顧平八郎方へ忍参り及面会、剰へ違作打続き諸民難渋に及び、一 体御政事向に付平八郎存意に不応儀間々有之、世を憂ふる心難堪間、 民を弔ふ大義を唱ヘ、往々王道に帰る様致し度、就ては謀計を以て奉 行を討取り、大坂御城を始め諸役所并に市中共焼払ひ、豪家の金銀を 窮民へ分遣し、一且摂州甲山へ可楯籠心底の旨平八郎申聞、近国へ告 知らする由の檄文読聞せ、右書中には無此上恐多文言も認有之を不容 易儀と心付、徹心致す廉も有之迚右企に一味連判致す始末、重々不届 至極に付、存命ならば引廻の上於大坂磔可申付処、対公議恐入候儀と 改心致し、賊徒発起以前右謀計の次第及密訴に付、御仕置御宥恕の上 取来る高の儘、御譜代被成下小譜請入可被仰付処、自殺致間其旨可存。
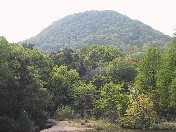 現在の甲山(大塩二郎氏提供)
現在の甲山(大塩二郎氏提供)