浦
へ
出
せ
る
触
書
二月十九日 諸家様・御留守居様・御役人中様
浦触書の写
此度於大坂不容易儀相企候、大塩格之助父平八郎へ致徒党候忰格之助并瀬田済之助・渡辺良左衛門・近藤梶五郎・庄司儀左衛門、其外名前不知者行衛不相知、船にて逃去候程難計候間、怪しき者は勿論廻船・小船・魚船等にて、他国相頼候共、決貸申間しく、如何体にても手当致取逃不申様其所へ留置き、早々大坂町奉行所へ訴候へば、為褒美銀百枚、手伝候者へ相応の褒美可差遣候絛、此旨相心得津々浦々にも不洩様早々相触候者也。
但此御触状先格の通り浦継ぎ無滞相廻触留より、大坂東番所へ持参可致候也。
大
塩
与
党
の
人
員
及
武
器
悪党者乱妨の次第
 |
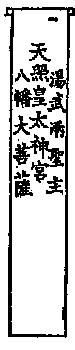 | 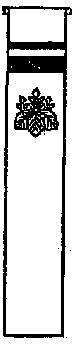 | |
又題目 の印も 有之。 | 三神一 は上の 図の如 く、一 は東照 太権現 とす。 | 平八郎 先手持 参目標 旗 桐 の紋は 今川家 の心意 |
-
(この処行列あれども前編二七九頁に出でたれば爰に略く)
「大塩騒動に関する落首 その5」
一、大坂勘助島天満屋忠兵衛方に罷在候
| 当酉十四歳 | 松本林太夫 | 淡路町藤井省吾女房連れ子松本官吾へ遣し候由 |
右の者七ケ年已前より平八郎に寄宿致し有之候処、此度一味致し、十九日市中乱妨に及び候砌、淡路町堺筋にて散々被打乱候節逃去候由申之。右林太夫白状の次第にて右人数の次第粗方相知れ候趣。
一、武□拾匁筒五挺、内二挺は成瀬正兵衛・八田衛門太郎方にて奪取る。外に三匁筒七挺・大筒・鍬筒は兼ねて丁打□みに公儀より拝借の分。
鉄筒
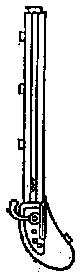
|
| 車に載せ用ふ |
筒長四尺余、台共五尺、金象眼登龍の紋あり。其外七拾目筒、銀象車輪の紋。
凶
徒
人
相
書
再三相廻り候人相書
河井郷右衛門 正月下旬出奔
年齢四十歳計り・顔白き方・鼻の上に疱瘡の跡あり・右の耳たぶ色変り有之。眉毛常体・目常体少し赤き方・背中肉・月代薄く髪赤き方・舌常体。
大井正一郎 玉造組与力 年齢廿五六歳計り・背高く痩せたる方・顔細長く色赤黒き方・眉毛濃き方・眼常体・耳常体・舌静なる方。
西村利三郎 廿四五歳計り・背低き方、下略。
志村周次 江洲小川村 三十歳計り・背高く中肉、下略。
堀井義三郎 播州加東郡西村堀井源兵衛忰 廿三四歳計り・背常体、下略。
曾我岩蔵 平八郎家来 四十六歳計り・背低き方、下略。
阿部長助 同断天満五丁目阿部屋久左衛門弟 二十歳計り・中背中肉、下略。
喜八 平八郎仲間 、五十二三歳計り・中背中肉、下略。
佶助 右同断 五十歳計り・背低き方。
忠五郎 右同断 四十歳計り・背高き方、下略。
落
文
の
写
落文の写
- (前編巻之六、二七一頁に既出に付き略す)
「大塩騒動に関する落首 その4」
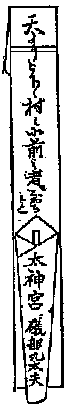 | 右黄色の絹に包み上書 但この紙一枚に板を摺り、板木は横に四枚・五枚宛ならん。摺後につきたる者也。此写初壱枚字竝び、大抵本紙の趣なり |